【スポンサーリンク】
リズムで曲調が変わる?
リズムは、曲の雰囲気に影響する重要な要素です。
同じメロディーでも、リズムが違うと、全く違う曲に聞こえることもあります。
今回は、リズムの違いによる曲調の変化を見ていきましょう。
リズムを変えて演奏すると?
例えば、こんなメロディーがあったとします。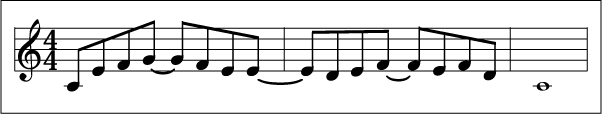
これを、いろいろなリズム(テンポ)で弾いてみましょう。
(「リズム」は「テンポ」に支配されます。
かなり難しい話になりますので、興味のない人は
この括弧書きの中は読み飛ばしてしまってかまいません。
「リズム」の説明はココで
「テンポ」の説明はココでしていますね?
実際には「リズム」と「テンポ」は異なるものですが、
リズムを変える=テンポを変える
というのは矛盾しないのです。
なぜならテンポはリズムに内包されるからです。
なおかつ内側からリズムを支配しているのがテンポです。
リズムは規則的に鳴る音楽の"規則"を作り出すものです。
テンポは、その規則の速さを決めるものです。
どうですか?意味が分からないですよね?
皆さんが何気なく音楽を聴いているときに、テンポが変わったら
何となく「あ、リズムが変わったな」と思いますよね?
それで良いのです。
「リズムを変える」というのは「テンポを変える」ということも含まれます。
しかし、同じテンポでも、異なるリズムになることもあります。
それを説明しているのが今回のページです。
同じメロディーでも、リズムのテンポを変えれば印象も変わります。
同じテンポでも、リズムの種類を変えると、やはり印象が変わります。
そんなリズムによる曲調の変化を学んでいきましょう。)
最初は、オーソドックスにBPM=100くらいで弾いたものですね。
ごく普通のメロディーですね。
次は、BPM=180のスピードで弾いてみました。
どうですか?
大分雰囲気が変わりましたね。
こんな風に、昔の曲や、しっとりとした曲をスピードアップして、
パンク・ロックやポップスっぽくカバーする手法は良く使われます。
3番目は逆に、スピードをもっと遅くしてBPM=60で弾いてみました。
スピードがゆっくりになると、かなりしっとりとした雰囲気になりますね?
先ほどとは逆に、元あった曲をスピード・ダウンしてバラード調にする。
という手法も、よく使われています。
他にも、ウラを強調しながらゆったりと弾いてレゲエ調にしたり、
ちょっと跳ねるようなリズムに変えて童謡調にすることもできます。
こんな風に、リズムひとつで、曲の雰囲気がガラっと変わるんですね。
シャッフルのリズム
もうひとつリズムの例を見てみましょう。
上の例と同じメロディーを、今度は跳ねるようなリズムで弾いています。
このような跳ねるリズムを「シャッフル」と言います。
連続した二つの音符のうち、初めの音符は長めに、ふたつめの音符を短く演奏します。
シャッフルはジャズやブルースなどの音楽で良く使われます。
「スウィング」なんて呼ばれることもあります。
シャッフルの基本は、3連符のうち、真ん中の音符を取り除いたリズムです。
楽譜上は普通に四分音符や八分音符として書かれることが多いです。
そのときは「この楽曲はシャッフルのリズムですよ」
という記号が書かれています。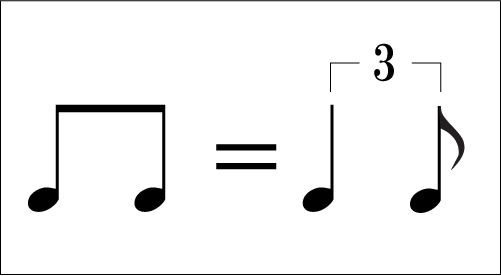
シャッフルのリズムは、厳密に1拍を3等分したものではなく、
微妙に前後の音符の長さが変わってくることもあります。
作曲者の意図や演奏者の解釈によってニュアンスが変化するためです。
その違いが、演奏者の微妙なノリを表すんですね。
正確なリズムやテンポにとらわれないノリもあるんですね。
【スポンサーリンク】
リズムで曲調が変わる?関連ページ
- 手拍子も音楽?
- 突然ですが、皆さんは応援などで手拍子を打ったことはありますか? パンパンパン・パンパンパン・パンパンパンパンパンパンパン、 という、3.3.7拍子などが有名ですね? ああやってみんなで合
- 拍と拍子の関係
- 楽譜を見ると、ト音記号などの横に、分数のような数字が書いてあります。 あれを「拍子記号」と言います。 音楽には"拍子"という大きな柱があり、それにそってリズムが作られます。 拍子記号は
- いろいろな拍子
- 前回は「拍子記号」について説明しましたね? 音楽に使われる拍子は、4分の4拍子だけではありません。 他にもいろいろな拍子があります。 よく使われる拍子 数字は無限ですから、拍子記号も
- テンポとは曲のスピードのこと
- 楽曲のムードや雰囲気を決定する重要な要素のひとつに"テンポ"があります。 テンポとは「その曲をどれくらいの速さで演奏するか?」をあらわしたものです。 いわば、楽曲の演奏スピードのことですね。 テ
- 速さを決めるテンポ記号
- 前回は、テンポを言葉で表現する速度記号を説明しました。 もうひとつ、テンポを表す方法があります。 それが、テンポのスピードを数値化して、数字で楽譜に書き込む方法です。 テンポを数字で書
- ウラってどこだ?
- ポップスやロックなどでは「ウラにアクセントを入れる」なんて言ったりします。 この"ウラ"って一体、どこなんでしょうか? ウラは偶数の拍 ウラという概念を知るために、まずはこの演奏を聞い
