【スポンサーリンク】
幹音と派生音
音楽を作ったむかしの人は、音の名前を付けるときに、
なぜ「ドレミファソラシ」という7つの音しか作らなかったのでしょうか?
どうして、わざわざややこしく
♯や♭を使うようにしたのでしょうか?
これにはいろいろな説があって、はっきりとはしていないません。
もともとは「ドレミファソラシ」という7つの音しか無かった。
残りの音は、後から作られたという説が有力です。
後から出てきた半音間隔の音を表すために♯や♭の記号が追加で作られた。
と考えられています。
白が幹音・黒が派生音
本当の経緯はどうなのかは分かりません。
とにかくそんなわけで、もともとあった「ドレミファソラシ」の7つの音を
"幹音"(かんおん)と言います。
ピアノの白鍵にあたる音ですね。
幹音に#や♭の記号を付けて表す音を"派生音"と言います。
「幹音から派生した音」という考え方なのでしょう。
これは、ピアノの黒鍵にあたる音になります。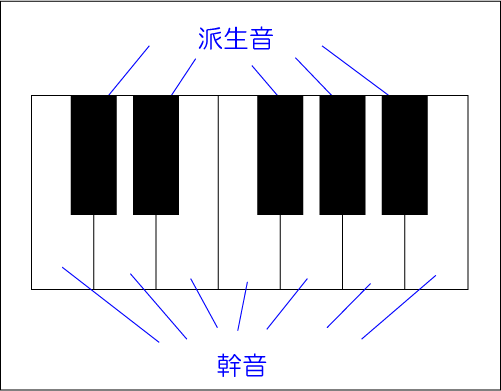
異名同音
前回、#(シャープ)と♭(フラット)についての説明のとき、
ド#とレ♭の音が同じになりましたね?
こういった音を「異名同音(いめいどうおん)」と言います。
音名は異なるけれども、実際の音はおなじ。
という異名同音は、以下のような組み合わせがあります。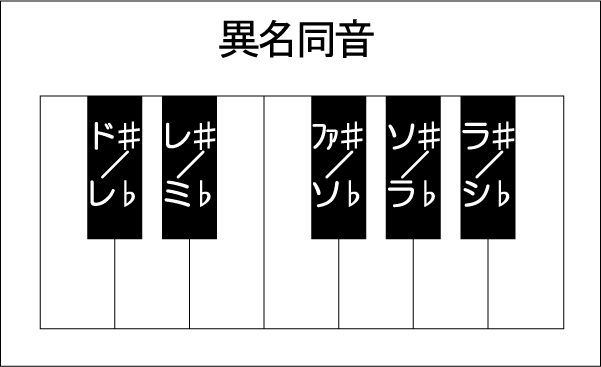
これをそのまま丸暗記する必要はありません。
ただ、楽譜上でレ♭やド#の音が出てきたときには、
どこを弾けば良いのか、すぐに分かるようにしておきましょう。
慌てずに「レ♭は、レを半音下げた音だな」とか
「ミ♯はミを半音上げた音だ」と考えましょう。
【スポンサーリンク】
幹音と派生音関連ページ
- 音程とは音の距離のこと
- 今回は「音程」について説明します。 音程は、英語ではInterval(インターバル)と言います。 その名のとおり、2つの音の高さの差や違いのことを示します。 ひとつの音と、もうひとつの
- たくさんある音の名前
- 突然ですが「音の名前」がどんなものか、頭に思い浮かべてください。 たいていの人は「ドレミファソラシド」という言葉が頭に浮かぶと思います。 でも実は、音の名前はそれだけではないのです。
- 音の名前が変化するとき
- 「ドレミファソラシド」は"階名"だ。 という説明を前回にしましたね? この階名は、同じ音でも違う呼び名になることもあるんです。 それはなぜなのでしょう? 調によって音名が変わる
- 半音と全音の違い
- 突然ですが、音程には「半音」と「全音」があります。 半音は、その名の通り、全音の半分です。 半音ふたつで全音になります。 全音のことを、1音(いちおん)と呼ぶこともあります。 全
- シャープとフラットで微妙な音階を表現
- 以前、音の名前(階名)には「ドレミファソラシド」あると説明しましたね? しかし、それだけで全ての音を表すことはできません。 楽器上には、半音間隔で音が並んでいます。 こんな
- オクターブは音の1周
- みなさんは「オクターブ」という言葉を聞いたことがありますか? よく「緊張すると声が1オクターブ上がる」なんて言いますよね? このオクターブというのは、言ってみれば"音の一周分"なのです。
- ト音記号とヘ音記号
- 楽譜を見てみると、五線譜の一番左側にクルクル回った変な記号がありますよね? あれは「音部記号」と言って、楽譜の基準を示す記号です。 音部記号の役割 音部記号には、五線譜上で「ドレミファ
