【スポンサーリンク】
拍と拍子の関係
楽譜を見ると、ト音記号などの横に、分数のような数字が書いてあります。
あれを「拍子記号」と言います。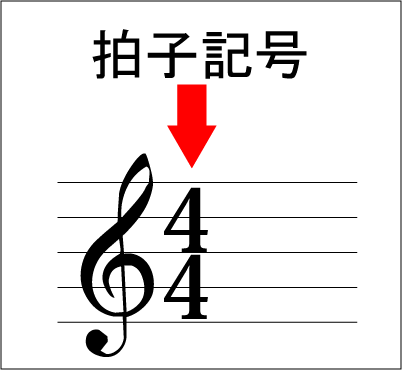
音楽には"拍子"という大きな柱があり、それにそってリズムが作られます。
拍子記号は、その曲をどんな拍子で演奏するかが表されています。
拍ってなに?
拍子というものを説明する前に、"拍"(はく)とは何か?
を理解しておきましょう。
「拍」とは、音楽の流れの中で基本となる、規則的なリズムのことです。
難しく考えることはありません。
音楽を聴きながら、手拍子をしますよね?
あの手拍子一回分が、一拍だと考えれば良いでしょう。
多くの楽曲では、"四分音符"ひとつを一拍とするのが基本です。
「四分音符」が何かは、コチラでやりましたね?
拍子記号の読み方
では、拍子の話に戻りましょう。
楽譜の左端に書いてある分数のような数字。
これは、"拍子記号"と言って、その曲の拍子をあらわしています。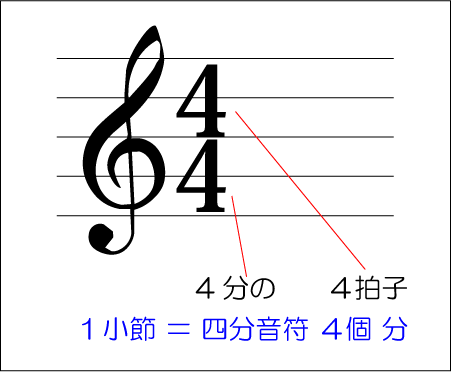
読み方は分数とおなじで、下から上へ「◯分の×拍子」と読みます。
上の例は「4分の4拍子」(よんぶんのよんびょうし)と読みます。
拍子記号の分母(下段の数字)は、拍の基準となる音符をあらわします。
この数字が"4"だったら、"四分音符"が基準になります。
上の数字は、「その音符を何回打つか」をあらわしています。
この数字が"4"だったら「4回打ってひとかたまり」になります。
「ひとかたまり」とは"1小節"のことを言います。
(小節についてはコチラで説明しましたね?)
拍子記号には、1小節のうちに"基準となる音符"を"何回打つか"
が書かれています。
上の画像の「4分の4拍子」では「1小節に四分音符を4回打つ」
ことになります。
これで、拍子記号の読み方もバッチリですね!
【スポンサーリンク】
拍と拍子の関係関連ページ
- 手拍子も音楽?
- 突然ですが、皆さんは応援などで手拍子を打ったことはありますか? パンパンパン・パンパンパン・パンパンパンパンパンパンパン、 という、3.3.7拍子などが有名ですね? ああやってみんなで合
- いろいろな拍子
- 前回は「拍子記号」について説明しましたね? 音楽に使われる拍子は、4分の4拍子だけではありません。 他にもいろいろな拍子があります。 よく使われる拍子 数字は無限ですから、拍子記号も
- テンポとは曲のスピードのこと
- 楽曲のムードや雰囲気を決定する重要な要素のひとつに"テンポ"があります。 テンポとは「その曲をどれくらいの速さで演奏するか?」をあらわしたものです。 いわば、楽曲の演奏スピードのことですね。 テ
- 速さを決めるテンポ記号
- 前回は、テンポを言葉で表現する速度記号を説明しました。 もうひとつ、テンポを表す方法があります。 それが、テンポのスピードを数値化して、数字で楽譜に書き込む方法です。 テンポを数字で書
- リズムで曲調が変わる?
- リズムは、曲の雰囲気に影響する重要な要素です。 同じメロディーでも、リズムが違うと、全く違う曲に聞こえることもあります。 今回は、リズムの違いによる曲調の変化を見ていきましょう。 リズ
- ウラってどこだ?
- ポップスやロックなどでは「ウラにアクセントを入れる」なんて言ったりします。 この"ウラ"って一体、どこなんでしょうか? ウラは偶数の拍 ウラという概念を知るために、まずはこの演奏を聞い
